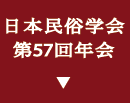 |
| |
基調講演
民俗学の周縁性と実践
伊藤 亞人 (東京大学)
民俗学という学問は、その対象である民俗知識と思考の特質を反映している点で、まさしく土着の学問である。民俗知識は地域の生活経験の中で蓄積されてきた知識であって、論理的体系性を成さない個別知識の集合である。東アジアにおける儒教や仏教などの論理体系的な教えや近代の科学知識を拠り所とした学問が、抽象的な論理によって人間や世界の普遍像を説き、その体系の中に個別の経験や事例を位置づけて解釈したり予測したりする思考を重視するのとは異なり、民俗知識は個別の物と場に即した具体的な知識であり、もともと生活実践と不可分のものであるが、普遍性を論理体系的に説く東アジアの大伝統や近代の科学主義と世界システムのもとでは周縁的なものと見倣されてきた。しかし、開発の現場で民俗知識に拠る実践志向的な開発手法が再評価されているとおり、地域社会の活性化においても民俗学の実践的な手法を肯定的に位置づけることが求められている。
パネリスト【1】
野の学問の苦境
佐藤 健二 (東京大学)
「野」と「実践」という二つが焦点であり、どう結びつけるかが問われるべき課題だと受け止めた。「野の学問」は、これを「ノの」と重ねて読めば美しくひびき音は、学ぼうとする人を広いフィールドという採訪の現場へと誘うだろうし、「ヤの」と強く発音すれば、野党や野に下るの語とともに、制度の外で育った民間学の対抗性という特質を浮かびあがらせる。趣意書は、ややスローガン的に、「研究対象の在野性」と「研究主体の在野性」と述べるが、位置だけをそのように固定的にとらえるのは十分でない。〈対象〉と〈主体〉だけでなく、もうひとつ重要なのが〈方法〉である。「野」も「実践」も、まさしくこの〈方法〉にかかわらせて理解すべきではないか。
「民俗学」と呼ばれてきた学問が、いかなる批判の「実践」として立ち現れてきたのか。その歴史をあらためて踏まえ、現在を考えなおす必要があるだろう。私自身は、これまで近代日本語における二重構造、声(口承)への注目の方法性、学問運動のネットワークとしての郷土研究、広場として雑誌の意味、「定本柳田国男集」の功罪、新語論の射程、「複数の柳田国男」など多くの論点を組み合わせながら、柳田国男を中心に、その学問の可能性を考えてきた。〈書かれたもの〉がもつ社会的装置としての意味と、そのなかを生きる読者という主体の実践が作り上げる「読書空間」モデルにおいて民俗学の実践を位置づけるなら、それは「リレーショナル・データベース」のメタファーで指し示せるであろう資料空間の構築である。それがいかなる主体によって、またいかなる場において形成され、変形され、批判され、再編成されていったか。
このリレーショナルなデータベース構築の実践が直面している困難にこそ、現代の民俗学の苦境がある。その問題は、おそらくひとり民俗学だけに限られない、学際的な拡がりを有している。そことどのように取り組むべきか。
パネリスト【2】
伝統の創造と学校教育
小国 喜弘 (東京都立大学)
野の学問からアカデミズムへと民俗学が変貌を遂げた時、民俗学と教育学との間に大きな隔たりが生まれることになったのではなかろうか。1935年民間伝承の会の設立当時、「野の学問」としての民俗学を支えたのは小学校教師であったし、よく知られているように柳田国男の民間伝承論は学校教育への関心が強かった。共同体の再生産と文化の世代間継承を重要な主題とする点からすれば民俗学と教育学は本来関わりの深い学問であった。しかし、アカデミズムとしての民俗学は、学問としての厳密さ・資料操作法の客観性を重んじる中で、子どもの教育環境をトータルに捉え、その改善の方途を探ろうとすることに禁欲的であったのではないだろうか。
近年、様々な地域における民俗芸能の伝承を考えたとき、学校教育は重要な役割を果たす存在になりつつある。保存会などが学校で芸能を教える動きが活発化しているからだ。
ただし学校での取り組みは、単に学区にある芸能を子ども達に忠実に継承するという試みに止まらない複雑な様相を帯びている。教師たちはしばしばその地域に全くない芸能を他地方から学び、その芸能を運動会用等に大胆に再構成して子ども達に伝えようとしている。時には学校で子どもたちが学んだ他地域の芸能が学区での祭に上演され、郷土の芸能として根付くことすらある。付け加えれば、文部科学省の伝統文化教育推進事業など、民俗芸能の教育を、ナショナルな統合に改めて利用しようとする動きも活発化している。
報告では、学校を舞台とした民俗継承の取り組みを手がかりとして、民俗学と教育学とを改めて架橋する可能性について模索したい。しかしそれは既存のアカデミズムの閉塞性を打破し新たなアカデミズムを構築しようとするもくろみからではない。弛緩しつつある社会の共同性の再構築とそこに住む人々の幸せをいかに追求するのかという実践性を一方の課題としつつ、民俗と教育にかかわる新たな理論構築をなし得ないか、考えてみたいのだ。今回は、その第一歩としての問題提起を行ってみたい。
パネリスト【3】
「野の学問」の歴史的屈折と学問と社会の新境地
鬼頭 秀一 (東京大学)
どのような学問領域(discipline)においても、学問の制度化(disciplinization)は必然的に起こる。方法論が整備され、教科書ができ、学会誌により学問として認められたものだけがアカデミックな業績として引用され、蓄積されていく。アカデミックなポストが整備され、学問を職業として行うことができるようになり、一定の方法論的枠組みの中で対象を把握できるようきちんと訓練(discipline)され、弟子が育っていく職業的養成機関が整備されていく。その中でアマチュアリズムは排除されるか棲み分けがなされる。しかし、制度化された学問はときとして「社会」との回路を失い、蛸壺化し、まさに学問のための学問に埋没していき、一方で権威づけられていくことにより「権力」として機能していく。1960〜1970年代にはそのような学問に対する問い直しが行われ、科学論や学問論が盛んに議論された。その当時、民俗学はまさに「野の学問」であり、制度化された学問にはないエネルギーを感じた人たちにとって大変魅力的であった。しかし、民俗学の内部では制度化の必要性が感じられ押し進められていったように思う。いま、民俗学で「野の学問」が再考されるという歴史的屈折を考えたとき、「野の学問」の意味について現代的な意味づけをするには意義深いかもしれない。制度化を打破し、「社会」との回路を創り出していくため、「学際的(inter-disciplinary)」方法論が模索されたりしたが、近年では、研究者自身が学問領域を越境していく「trans-disciplinary」なあり方や、「問題指向型(problem-oriented)」なあり方が注目されている。その真髄を一言で言えば、「現場(field)」を狭い学問的方法論で切り取るのではなく、その全体をまるごと捉えるための方法論ではないだろうか。そこにこそ「discipline」を越える可能性が見いだされる。「野の学問」が現代的意味を持ち、学問と社会の間に良好な関係を築こうとするのであれば、「現場をまるごと捉える」という意味での「野」の学問がいま求められているのではないだろうか。